【STAGE 3・レンガ職人に挑戦してみた】
レンガ職人に挑戦と言っても、ジオラマの世界での話である。最近、フィギュアの制作に挑戦しているが、ジオラマ制作も、思い出したようにやりたくなった。
今から数十年前、模型の列車(Nゲージ)を走らせようと思ったことがあった。しかし、どちらかと言うと、列車を走らせるより、列車が走る、あるワンシーンの風景を制作したかったのが理由である。例えば、現実には走行不可能な崖っぷちにレールを敷くというような在りもしない世界に入り込むことであった。
結局、列車を走らせることも、断崖絶壁の風景制作も実現しなかった。今回、Nゲージ列車はさて置き、単にジオラマとしての『レンガの壁』を積み上げることにした。まさに、ボケ老人の思いつきと言うほかない。積み上げ職人の必需品は「水準器」である。いくら、ジオラマとは言え形から入らなければならない。


レンガ単体でも美しさはあるが、積み上げられたレンガや通路に敷き詰められたレンガには美しさを感じる。更に、そのレンガを引き立たせているのが、レンガとレンガの繋ぎ目・接合部の「目地」にあることは否定できない。この「目地」実はレンガを積み上げる上で必要不可欠なもので、美しさを出す為にだけ設けられているものではないのである。
「目地」は、レンガ(タイル)を組積する場合の接着剤の役割以外に重要な働きがある。レンガは焼物であるため、出来上がった製品は全てが正確な規格品とはならず、多少なりとも誤差が生じてしまうのである。その誤差を調整するのが「目地」と言うわけであるが、意匠とし、美しさを出すことにもなる。
元々、レンガは強度性はなく、大規模建築の積み上げには適さない。建築物の内部には強度の強い材料を使用し、仕上げ・装飾用として用いられるのが一般的である。が、耐火レンガの窯だけは装飾用ではない。暖炉やピザを焼く窯には耐火レンガが用いられている。
さて、レンガ職人の話に戻そう。制作レンガの素材は発泡スチロールに薄く粘土を食いつかせた。レンガ一個・一個の仕上がり凹凸、着色も含め焼き具合の差を出すこととした。あくまでも、レンガが使用され出したメソポタミア文明の時代に遡った。そのために積み上げ接着剤(目地)の雰囲気も用具は一切使用せず、手作業とした。

実際の建築物でも、装飾用として壁一面レンガを積み上げたものを見ることが有るが、パネルで出来た重量感の無いものになってしまう。余りにも、整い過ぎたレンガの壁は魅力に欠ける。西洋の一個一個手作業で積み上げた城や要塞などは美しい。最後の仕上げは「目地」の着色である。意外と石膏のようなものが多く見かけるが、「モルタル」のグレー系で強度感を出してみた。

ボケ老人の意味の無い7段レンガ積み上げであったが、これで完成としよう。

ブログ「これでいいのだ」
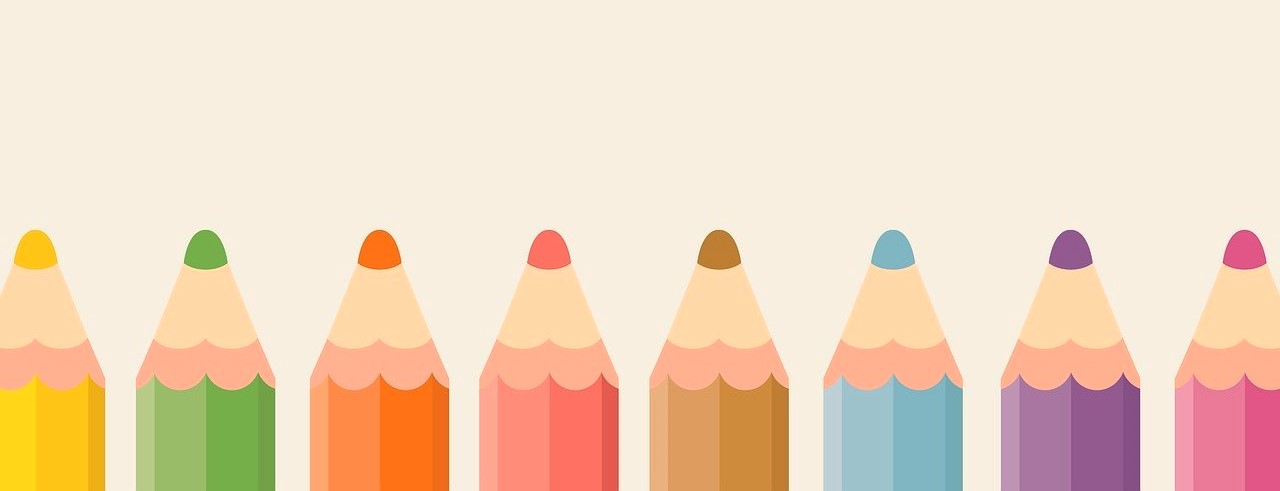





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません